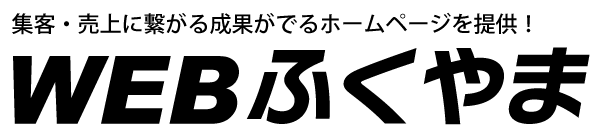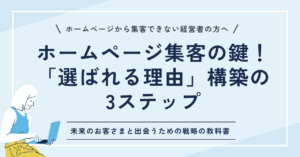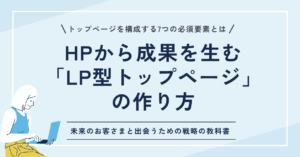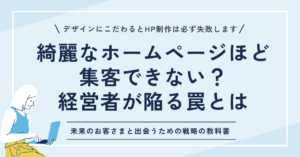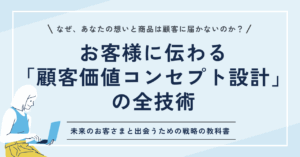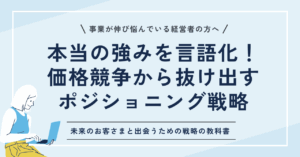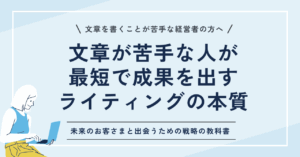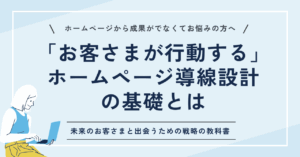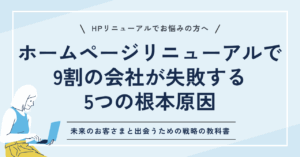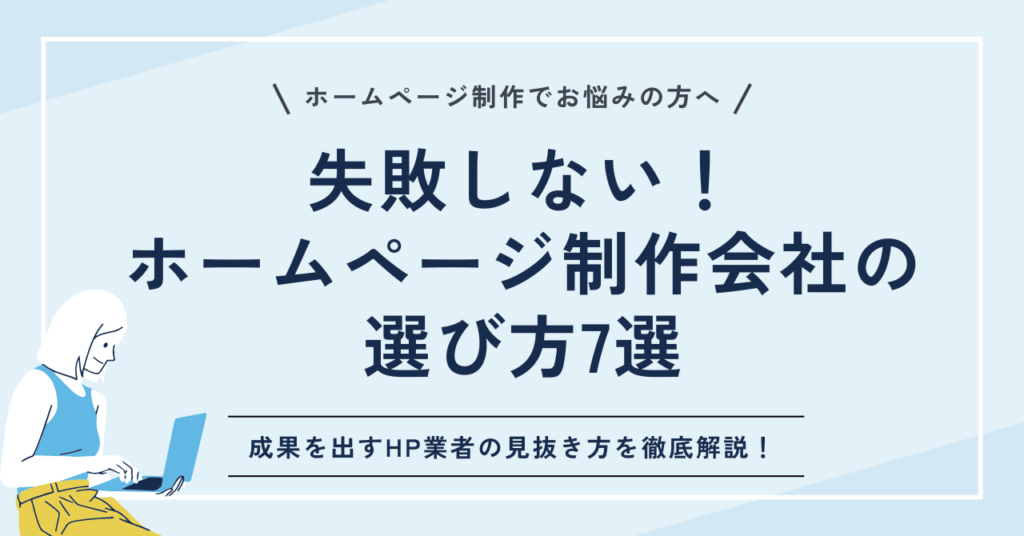
「高額な費用をかけて、ようやくホームページが完成した…」
「デザインも綺麗だし、これでウチもWEB集客ができるはずだ…」
多くの経営者様が、そう期待に胸を膨らませてホームページを公開します。
しかし、その数ヶ月後、現実はどのようなものになっているでしょうか。
- アクセス解析を見ても、訪問者はほとんどいない…
- 鳴るはずだったお問い合わせの電話は、沈黙を保ったまま…
気づけば、高額な投資の結晶であったはずのホームページは、誰の目にも触れることのないまま、ただサーバー上に存在するだけのデータと化してしまっています。
見込み客からのアクセスはほとんどなく、当然、一件のお問い合わせも生み出さない。
結果として、投じた莫大な費用が全く回収できず、事業上の成果に何ら貢献しないという事態に陥ります。
「一体、何がいけなかったのだろうか…」
「制作会社の言う通りにしたはずなのに、なぜ成果が出ないんだ…」
もし、あなたがこのような経験や漠然とした不安を感じているならご安心ください。
その悩みは、決してあなた一人のものではなく、WEB集客で失敗する経営者の9割が共通して陥っている罠なのです。
この記事では、あなたが二度とホームページ制作で失敗しないために、本当に必要な知識だけを凝縮しました。
高額な投資を無駄にせず、あなたの事業を本気で加速させるための内容です。
失敗の本質から成功への具体的な道筋までを論理的に解き明かしていきますので、ぜひ、最後までお付き合いください。
第1章:「売れるホームページ」の再定義

断言します!
失敗の根本原因は、あなたの事業内容や努力不足ではありません。
その原因は、ホームページ制作の出発点である「ホームページとは何か」という定義そのものを、根本的に誤解していることにあります。
多くの経営者が、ホームページの良し悪しを「見た目のデザイン」で判断し、その美しさにばかりこだわってしまいます。
さらに深刻なのは、その受け皿となる制作会社の9割以上も、クライアントの成果ではなく「いかに綺麗なデザインを作るか」を自社の強みとして掲げているという現実です。
この、成果という本来の目的を置き去りにした「見た目重視」の発注者と制作者の組み合わせが、すべての失敗の根本原因なのです。
本稿でお伝えしたい、たった一つの真実。
それは、成果を出すホームページとは、単なるWEBサイトではないということです。
24時間365日働き続け、見込み客を見つけてあなたの事業価値を伝える。
最終的に顧客へと転換してくれる、極めて優秀な『デジタル営業マン』に他なりません。
そして、事業全体のマーケティング活動を支える、揺るぎない『戦略拠点』がホームページなのです。
この「戦略拠点」という視点を持つだけで、あなたの制作会社選びの基準は180度変わるはずです。
「デザインの美しさ」や「機能の多さ」といった表面的な要素がいかに些細な問題であるか、ご理解いただけることでしょう。
第2章:ホームページの「役割」を明確にする

「どのようなホームページにしたいですか?」
と、制作会社の担当者から問われる場面を想像してみてください。
その時、あなたは何と答えるでしょうか?
- 「同業他社のA社みたいな、格好いいデザインにしてほしい」
- 「お客様の声や、実績紹介のページは必ず入れたい」
- 「ブログ機能と、できれば予約システムもつけたいな」
もしも、あなたがいきなりデザインや機能の話から始めてしまうなら…。
既にプロジェクトの進行手順を誤っていると言わざるを得ません。
なぜならば、ホームページは、事業目的を達成するための「媒体」。
そして、デザインや機能はその「仕様」に過ぎないからです。
事業におけるあらゆる投資は、何らかの目的を達成するために行われるべきです。
そして、その目的が明確にすることではじめて、最適な「媒体」や「仕様」が決まります。
例えば、目的が「新規問い合わせを月10件獲得する」ことであれば、それに最適化された情報配置や導線設計が仕様の要件となります。
一方で目的が「採用応募者の質を高める」ことであれば、企業の理念や文化を魅力的に見せるための仕様が求められるでしょう。
目的が定まっていなければ、「どんなデザインが良いか」「どんな機能が必要か」という問いに対する判断基準そのものが存在しないのです。
この状態で制作を進めても、出来上がるのは「誰の、どんな課題を解決するのかが不明確な、目的のないWEBサイト」でしかありません。
まずは、経営者であるあなたが、WEBサイトという媒体に担わせる「役割」を定義する必要があります。
そのために、最低限、以下の「3つの問い」に対する答えを言語化してください。
①【Who】あなたのホームページは、「誰」に向けたものですか?
事業のターゲットとなる顧客は、誰で、その人物はどのような課題や欲求を持っているのでしょうか。
この具体的な顧客像(ペルソナ)が、WEBサイトが伝えるべきメッセージの方向性を決定します。
②【What】その顧客に対して、「何」を伝えますか?
あなたの事業が提供できる独自の価値(バリュープロポジション)とは一体何でしょうか。
なぜ、顧客は競合ではなく「あなた」を選ぶべきなのか、その理由がサイトの核となるコンテンツです。
③【How】どのようにして、顧客を「成果」まで導きますか?
ターゲット顧客があなたの価値を理解し、最終的に「お問い合わせ」や「購入」といった行動に至るまでのWEBサイト上の道筋(情報設計・導線設計)はどうあるべきか。
これがWEBサイトの構造を決定します。
以上の Who, What, How こそ、あなたのWEB戦略の根幹であり、制作会社に伝えるべき最も重要な要件といえます。
まずは、この3つの問いに対する答えを、A4用紙一枚でも構いませんので書き出してみてください。
これがあるだけで、あなたはただの「発注者」から、プロジェクトを主導する「戦略家」へと変わるのです。
優れた制作業者は、必ずこの戦略部分を深くヒアリングしてきます。
しかし、最終的な答えを持つべきは、事業の責任者であるあなた自身に他なりません。
この土台があって初めて、次の章で解説する「5つの失敗例」が、なぜ本質的に問題なのかをご理解いただけるはずです。
第3章:制作会社選びで失敗する5つの失敗例

第2章では、ホームページ制作は事業戦略の明確化から始まるべきだとお伝えしました。
この大前提を欠いたまま制作会社選びを進めると、ほぼ例外なくこれからお話しする「5つの失敗例」に陥ることになります。
これらは私がこれまで数多くのご相談に乗る中で、成果の出ないホームページに共通して見られた典型的なパターンです。
一つひとつ、なぜそれが「失敗例」となるのかを具体的に見ていきましょう。
失敗例①:「美しさ=デザイン」という致命的な誤解
第2章では、ホームページ制作は事業戦略の明確化から始まるべきだとお伝えしました。
この大前提を欠いたまま制作会社選びを進めると、ほぼ例外なくこれからお話しする「5つの失敗例」に陥ることになります。
これらは私がこれまで数多くのご相談に乗る中で、成果の出ないホームページに共通して見られた典型的なパターンです。
一つひとつ、なぜそれが「失敗例」となるのかを具体的に見ていきましょう。
失敗例1:「美しさ=デザイン」という致命的な誤解
結論から申し上げますと、WEBマーケティングの世界において、デザインとは「見た目の美しさ」ではなく「設計」を指します。
本来、WEBサイトにおける「良いデザイン」とは、明確な事業目的を達成するためのもの。
ターゲット顧客があなたの提供価値をスムーズに理解し、最終的にあなたが望む行動をストレスなく起こせるようにする、情報整理や配置、誘導といった「設計思想」そのものを指します。
「デザインの美しさ」を強みとしてうたう制作会社の多くは、クライアントから「格好いいホームページですね」と言われることを評価基準においており、この「設計思想」が大きく抜け落ちています。
結果として、見た目は美しいものの、情報が探しにくかったり、ターゲット顧客に価値や魅力が伝わらない、成果の出ないホームページが完成してしまうのです。
失敗例②:過剰な機能がもたらす逆効果
「せっかく作るなら、あれもこれもできるようにしたい」というお気持ちは十分に理解できます。
例えば、派手な動画、動きのあるエフェクトやアニメーション、予約システムなど、制作会社も様々な高機能オプションを提案してくるでしょう。
しかし、その過剰な機能が、かえって事業目的の達成を妨げる「逆効果」を生むことを理解しなくてはなりません。
人間には「選択のパラドックス」という心理が働き、選択肢が多すぎると、かえって脳が混乱し思考が停止してしまいます。
WEBサイトも同様で、機能や情報が多すぎると訪問者は認知的な負荷を感じ、本当に見てほしい情報にたどり着く前に離脱してしまうのです。
成果を出すホームページは、むしろ驚くほどシンプルに作られています。
それは訪問者に取ってほしい行動を一つに絞り、そこに至るまでの障害を徹底的に排除しているからです。
機能を追加する際は、常に「これは目的達成の助けになるのか?」という一点のみを問いかけるべきです。
失敗例③:価格だけで判断するリスク
複数の制作会社から見積もりを取り、最も安い業者に発注することは、一見すると合理的な経営判断に見えます。
しかし、ホームページ制作においては、この安易な価格比較にこそ大きな「リスク」が潜んでおり、「安物買いの銭失い」に直結するケースが後を絶ちません。
なぜ、制作費用に数十万から数百万円もの価格差が生まれるのでしょうか。
その差額は、単なるデザイン費やプログラミング費ではないのです。
格安業者の見積もりは、多くの場合、単純な「作業費」であり、あなたが言った通りのものを、言われた通りに作るだけ。
そこには第2章で述べたような戦略設計や、市場調査、競合分析といった工程は含まれていません。
一方、高額であっても成果を出す制作会社は、制作を始める前に、あなたの事業を深く理解し、成果を出すための設計に多くの時間を費やします。
この「戦略設計費」こそが、価格差の正体であり、ホームページがデジタル営業マンとして機能するための心臓部なのです。
失敗例④:「独自開発CMS」による“囲い込み”リスク
CMSとは、専門知識がなくてもホームページの一部を自分で管理・更新できる仕組みのことです。
このCMSを、制作会社が独自に開発したものを使っている場合は最大限の注意が必要です。
独自開発CMSでサイトを作ってしまうと、将来のリニューアル時に他社が手出しできなくなるという重大な問題があります。
システムの仕様が公開されておらず、ブラックボックス化しているため、他社は何もできないのです。
結果として、あなたは最初に依頼した制作会社に、保守管理や追加改修で言い値の費用を払い続けるしかなくなる可能性があります。
これは、デジタル時代の新たな「囲い込み」手法であり、経営上の大きなリスクとなり得ます。
失敗例⑤:「ゼロからの完全オリジナル制作」への固執
「テンプレートではなく、ゼロから作る完全オリジナルのホームページの方が、成果が出るに違いない」という考えも、根強い誤解の一つです。
フルオーダーメイドという言葉の響きは魅力的ですが、多くの中小企業にとっては、必ずしも最適解とは言えません。
現在、WordPressに代表される世界標準のCMSには、世界中のプロフェッショナルが開発した、非常に高品質で成果実証済みのデザインテンプレートが無数に存在します。
これらのテンプレートは、最新のWEB標準やSEO、多様なデバイスでの表示(レスポンシブデザイン)に最初から対応しているものがほとんど。
ゼロからこれらすべてを考慮してフルオーダーで制作すれば、当然、莫大なコストと時間が必要になります。
しかし、実績のある高品質なテンプレートをベースに、自社の事業戦略に合わせて必要な部分だけをカスタマイズする方法を取れば、コストと納期を大幅に圧縮しつつ、十分な成果を出すサイトを構築することが可能です。
「ゼロから作ること」自体を目的化してはいけません。
あくまで目的は「事業成果を出すこと」であり、そのための最も合理的で費用対効果の高い手段を選択するべきなのです。
第4章:成果を出す制作会社を見抜く「7つの必須チェックリスト」

第3章では、多くの経営者が陥りがちな「5つの失敗例」を解説しました。
これらはホームページ制作で失敗しないために、あらかじめ知っておくべき重要な注意点と言えます。
では、これらの失敗を回避し、自社の事業成果に貢献してくれる、本当に信頼できる制作会社はどのように見極めれば良いのでしょうか。
この章では、そのための具体的かつ実践的な「7つの必須チェックリスト」をご紹介します。
チェックリスト1:「設計思想」を語れるか?
デザインの説明を受ける際は、担当者が「格好いい」や「今風」といった主観的な言葉ばかり使っていないか注意すべきです。
そうではなく、「なぜ、このページ構成にしているのか」など、顧客心理や行動原理に基づいて説明できるかに注目します。
チェックリスト2:「ターゲット」を深掘りしてくれるか?
「あなたの会社のターゲット顧客は誰ですか?」という質問の有無ではなく、その「深さ」に注目してください。
「ターゲットは30代〜50代の経営者です」とあなたが答えたとします。
その回答に対し、「なるほど、承知しました」で終わってしまう会社は三流です。
一流のパートナーは、そこからさらに質問を重ね、ターゲットの解像度を上げようと努めてくれるかがポイントです。
チェックリスト3:「集客方法」まで提案してくれるか?
ホームページを作ること自体が目的化している制作会社は、「作って終わり」の無責任な仕事しかしません。
成果にコミットしているプロは、必ず「作った後、どうやって人に見てもらうか」という集客戦略までセットで考えてくれます。
打ち合わせの中で、担当者の口から「SEO」「MEO」「WEB広告」「SNS連携」といった、集客に関するキーワードが自然に出てくるかどうかに注目してください。
チェックリスト4:具体的な「実績」を語れるか?
重要なのは「何を作ったか」ではなく「作ってどうなったか」です。
本当に実力のある会社は、自社の仕事がクライアントのビジネスにどのような価値をもたらしたかを把握しており、それを誇りに思っています。
「どのような課題があったか → それに対してどのような施策を行ったか → 結果としてどのような成果が出たか」という、明確なストーリーを確認してください。
チェックリスト5:「公開後の運用」を視野に入れているか?
ホームページは公開がゴールではなく、スタートであり、ビジネス環境の変化に合わせて改善し育てていく必要があります。
「作りっぱなし」では、ホームページの価値は時間と共に劣化していってしまいます。
契約内容の説明の際に、サイト公開後の保守管理プランの内容を確認します。
技術的な保守だけでなく、アクセス解析レポートの提出や、データに基づいた改善提案といった、マーケティング視点でのサポートが含まれているかどうかがポイントです。
チェックリスト6:明確な「根拠」と共に説明してくれるか?
プロフェッショナルの仕事は、すべてに理由があります。
「なんとなく」や「最近の流行りだから」といった曖昧な理由で提案を行う会社は、思考が浅く、信頼に値しません。
すべての提案に論理的な根拠があるということは、その会社が一つひとつの施策を深く考え抜き、あなたの事業成果に対して真摯に向き合っている証拠だからです。
打ち合わせの中で、あなたの質問や要望に対し、担当者がどのように応答するかに注目してください。
チェックリスト7:「パートナー」として信頼できるか?
最後になりますが、これが最も本質的な項目かもしれません。
どれだけ優れた技術や理論を持っていても、最終的に仕事をするのは人と人です。
ホームページ制作は、その後の運用も含めれば数年単位の長い付き合いになるプロジェクトです。
事業の根幹に関わる重要な情報を共有し、時には難しい判断を共に乗り越えていく相手として、人間的な信頼関係を築けるかどうかは、プロジェクトの成否を大きく左右します。
専門用語を並べて話を難しくしようとせず、初歩的な質問にも誠実に答え、あなたの事業を成功させたいという「熱意」を感じられるか。
今までの6つの質問に対する相手の「姿勢」そのものが、この問いに対する答えとなります。
第5章:適正な「投資額」を見極める

第4章までのチェックリストを用いて複数の制作会社と打ち合わせを進めると、各社の質の違いが明確になってくるはずです。
しかし、最終的な意思決定の段階で、多くの経営者が再び頭を悩ませるのが「費用」の問題です。
この時、あなたは見積書に記載された金額の大小だけで判断してはいけません。
ホームページ制作の費用を、事業の成果に繋がる「投資」として捉え、その妥当性を見極める視点を持つことが不可欠です。
ホームページ制作の費用は何で決まるのか?
まず、見積もりの内訳を正しく理解する必要があります。
制作費用は、主に以下の要素で構成されています。
| 企画・戦略費 | 市場調査、競合分析、コンセプト設計など、成果を出すサイトの土台を作る費用 |
|---|---|
| 情報設計・デザイン費 | 戦略に基づき、サイト構造や導線を設計し、ビジュアルに落とし込む費用 |
| 実装・開発費 | デザインを実際にブラウザ上で機能させるための技術的な費用。 |
| コンテンツ制作費 | 掲載する文章や写真などを作成する費用 |
| プロジェクト マネジメント費 | プロジェクト全体の進行管理費 |
第3章で触れた格安業者は、このうち「企画・戦略費」や「情報設計費」をほとんど計上せず、主に「実装・開発費」だけで見積もりを作成しているケースがほとんどです。
「費用」ではなく「投資」として判断する
成果を出す制作会社に依頼すれば、費用は安くても数十万、通常は100万円を超えることが一般的です。
この金額を、単なる「コスト(経費)」と捉えると、どうしても安い方に流れたくなります。
しかし、視点を変えてください。
ホームページ制作は、コストではなく「投資」です。
それも、24時間365日働き続ける優秀なデジタル営業マンを雇用し、育成するための、極めて費用対効果の高い投資なのです。
LTV(顧客生涯価値)を基準に投資の回収ラインを見極める
では、その投資が自社にとって「妥当」か「過大」かは、どう判断すれば良いのでしょうか。
そのための最も重要な指標が「LTV(Life Time Value:顧客生涯価値)」です。
LTVとは、一人の顧客が、取引を開始してから終了するまでの全期間にわたって、あなたの会社にもたらしてくれる利益の総額を指します。
例えば、あなたの会社の顧客一人あたりのLTVが平均10万円だとします。
この場合、100万円をかけてホームページを制作したとして、何人の新規顧客を獲得できれば投資を回収できるでしょうか。
答えは極めてシンプルです。
100万円(投資額) ÷ 10万円(LTV) = 10人
つまり、制作したホームページから10人の新規顧客を獲得した時点で、あなたの投資は完全に回収され、それ以降に獲得した顧客はすべて純粋な利益になるということです。
このように、LTVを基準に考えることで、目の前の見積金額に惑わされることなく、極めて冷静かつ戦略的に投資判断を下すことが可能になります。
成果を出す制作会社は、このLTVの視点を持ち、あなたの事業計画に基づいた費用対効果を共に考えてくれます。
「今回の投資で、まずは〇社の新規顧客獲得を目指しましょう。そのために、このような戦略を取りましょう!」という対話ができる相手こそ、あなたが選ぶべきパートナーなのです。
おわりに:最高のパートナーと共に、事業を加速させるために

ここまで、成果を出すホームページ制作会社の選び方について、具体的なステップと判断基準を解説してきました。
もし、あなたがこの記事を最後までお読みいただいたのであれば、もはやホームページ制作会社を前にして、何を基準に判断すれば良いか分からずに不安になることはないはずです。
あなたは、制作会社に言われるがまま発注する「受け身の顧客」ではありません。
自社の事業戦略に基づき、プロジェクトを主導し、対等な立場でパートナーを評価・選定する「戦略家」としての視点を手に入れたのです。
ここで、改めて強調したいことがあります。
それは、ホームページは完成がゴールではなく、あくまで事業を加速させるためのスタートラインに過ぎないということです。
市場は変化し、競合は新たな手を打ち、顧客のニーズも移り変わります。
その変化に対応し、ホームページという戦略拠点を常にアップデートし、磨き込み、育てていく。
その運用プロセスこそが、持続的な成果を生み出すための鍵となります。
だからこそ、「業者」ではなく「パートナー」を選ぶことが重要なのです。
そんな長期的な信頼関係を築ける相手を見つけること。
この記事でお伝えしたかったのは、突き詰めればその一点に尽きるのかもしれません。
ぜひ、本稿で得た知識を羅針盤として、あなたの事業を次のステージへと共に引き上げてくれる、最高の戦略的パートナーを見つけ出してください。
最後に、もしあなたが、「自社の事業戦略を専門家の視点から客観的に整理したい」あるいは「どの会社を信頼すべきか最終的な判断に迷っている」といった課題をお持ちでしたら、一度、私にご相談ください。
私は、WEB制作に27年、WEBマーケティングに15年、SEOに17年携わってきました。
業界の黎明期から、ホームページが単なる「制作物」から「戦略拠点」へと進化する過程を最前線で見てきた専門家です。
そのため、この個別相談は大変恐縮ながら【毎月5社様限定】とさせていただいております。
ご興味をお持ちいただけましたら、以下の無料相談ページで詳細をご確認の上、お早めにお申し込みください。
あなたの事業が、力強く未来へ羽ばたくための一助となれれば、これに勝る喜びはありません。
ご連絡を、心よりお待ちしております。
お聞かせください!
「ホームページで結果が出ない…」と悩んでいるなら、今すぐ無料相談ください。
せっかく作ったホームページ。でも、お問い合わせが全然こない…そんな方がほとんどです。
ホームページの放置は、時間もお金もムダになります。
WEBふくやまは、WEB制作で20業種以上で多数の実績を持つWEBマーケティングの専門家です。
「誰に」「何を」「どう伝えるか」を徹底的に設計し、お客様を“申し込みにつなげる導線”に変えるホームページをご提案します。
まずは、無料相談でホームページの状態や課題を一緒に整理してみませんか?
お話を伺ったうえで、成果に繋がる改善ポイントや施策を丁寧にお伝えいたします。
まずは無料相談に今すぐお申し込みいただきお悩みを聞かせてください。
\ お気軽にご相談ください /